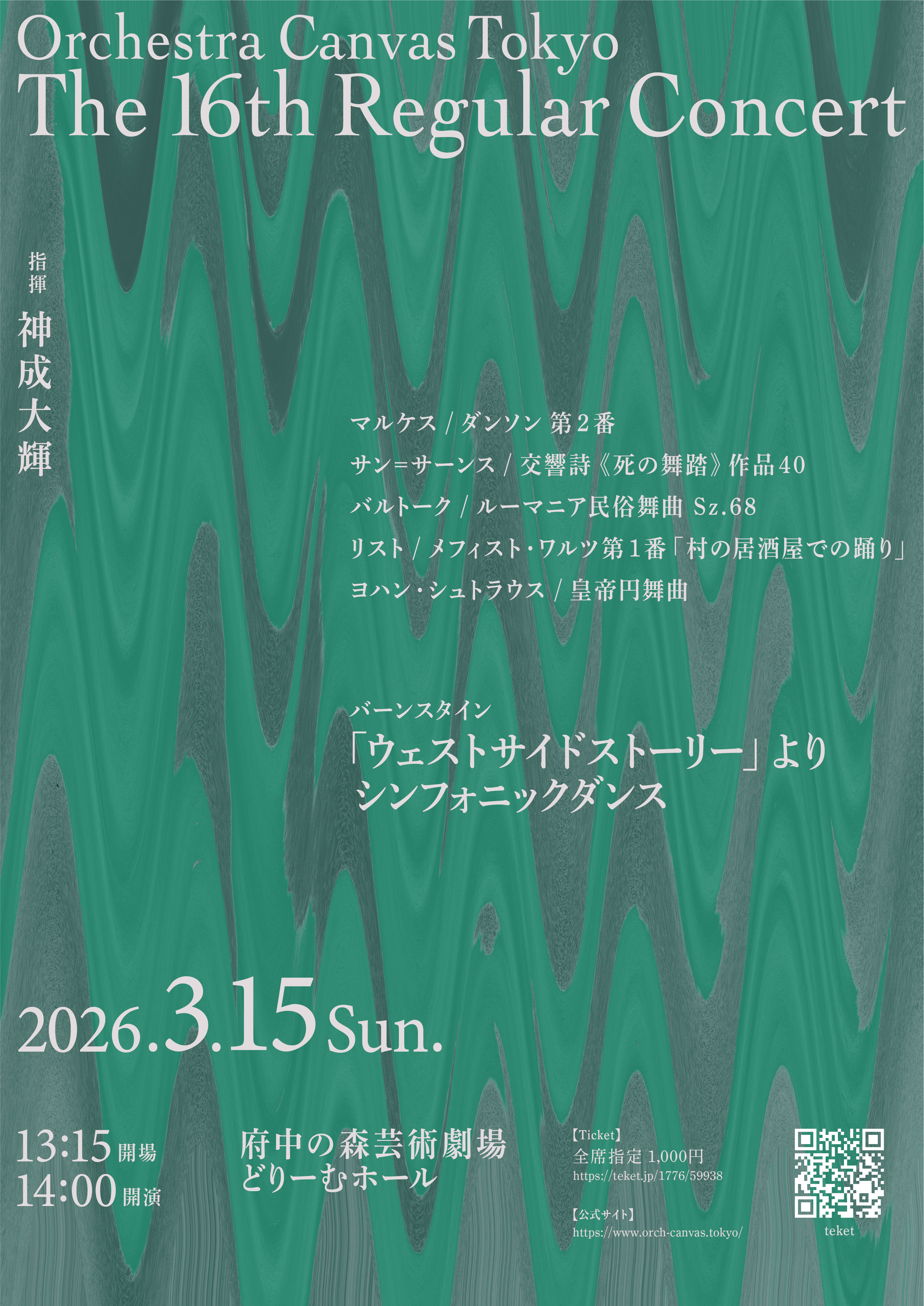鮮やかなメキシコの響きに続き、本演奏会は一転して暗闇へと誘われる。フランスの作曲家サン=サーンスの代表作、交響詩《死の舞踏》である。「フランスのモーツァルト」と称されるほどの神童であったサン=サーンスは、リストが創始した「交響詩」というジャンルをフランス音楽界に積極的に取り入れた人物でもあった。
本作は、フランスの詩人アンリ・カザリスの怪奇的な詩に着想を得た交響詩である。サン=サーンスはまず1872年に歌曲としてこの詩にメロディーを与え、その後1874年に管弦楽による歌のない交響詩へと発展させた。スコアの冒頭には、カザリスの詩から数行が引用されている。
ジグ、ジグ、ジグ、死神が拍子を取っている
踵で墓石を打ち鳴らしながら、真夜中に死神はダンスの調べを演奏する
ジグ、ジグ、ジグと彼のヴァイオリンで冬の風は吹き荒び、夜は暗澹としている
ボダイジュから呻き声が漏れ出し、蒼白い骸骨たちは闇を横切り、屍衣を纏ったまま走り跳び上がる
ジグ、ジグ、ジグ、めいめいが跳ね回り、踊る者たちの骨がカチカチいう音が聞こえるおい、ちょっと、と合図して突然彼らは輪舞を止める
そして押し合い圧し合い逃げて行く、一番鶏が鳴いたので
「死の舞踏(Danse Macabre)」は中世以来の伝統的な美術のモチーフであり、身分や貧富の差を超えて全ての人間に平等に訪れる死を象徴してきた。サン=サーンスは、この普遍的なテーマに対し、革新的な音響と巧みな管弦楽法によって独自の音楽的解釈を与えている。
ハープが午前0時の到来を告げ、死神に扮した独奏ヴァイオリンが登場する。このヴァイオリンはE線(最高弦)を半音下げてE♭に合わせるスコルダトゥーラ(変則調弦)を施されており、死神が調弦をするかのように、開放弦でラとミ♭の不協和音を鳴らす。このラ–ミ♭の音程はトライトーン(減5度または増4度、三全音)であり、中世より「悪魔の音程」として忌み嫌われてきた響きである。調性の中心を曖昧にするこの不吉な音程は、後の20世紀音楽における調性解体の萌芽を内包している。
死神に誘われ、フルートが魔法にかかったような主題を提示し、骸骨たちの狂乱の踊りが始まる。シロフォン(木琴)が骨の触れ合う音を模倣し、軽妙なリズムと鋭い管弦楽法が、グロテスクでありながら諧謔的な雰囲気を醸し出す。ワルツは次第に熱を帯び、狂乱の極みに達するが、突如、オーボエが夜明けを告げる雄鶏の鳴き声を模すと、饗宴は終局を迎える。骸骨たちは慌てて墓へと戻り、死神が名残惜しそうに最後の旋律を奏でると、朝の静寂の中に音楽は消え入るように終わる。
初演当時、変則調弦や不協和音の多用が物議を醸したが、やがて本作は広く受け入れられ、今日まで愛され続けている。サン=サーンスが描いた「死の踊り」は、恐怖だけでなく、どこか滑稽で人間的な側面をも併せ持つ。それは、死を忌避するのではなく、むしろ生の一部として受け入れようとする、フランス的な精神性の表れなのかもしれない。
(Pf. 阪内 佑利華)
参考文献
- 音楽之友社編, 1980,『最新名曲解説全集 管弦楽曲Ⅱ』(第5巻), 東京都, 音楽之友社.
- ジェームズ・ハーディング, ダニエル・M・ファロン著, 笠羽映子、片山雅子訳, 1994, “サン・サーンス,(シャルル・)カミーユ”, 柴田南雄, 遠山一行総監修,『ニューグローヴ世界音楽大事典. 7.』, 東京都, 音楽之友社.